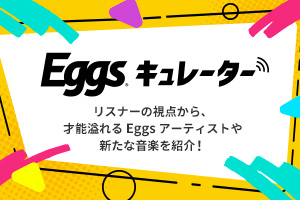2024年8月に六本木にオープンした新たなライブハウスSCHOOL LIVE & BAR TOKYO(以下、SCHOOL TOKYO)。ジャンルを問わず、個性が交錯する夜を生む場所として、時にライブ、時にDJイベント、時に演劇やトークイベントにも姿を変える柔軟さが特徴だ。約18年前に北京にオープンし、北京のライブハウスシーンの黎明期の一端を担ったSCHOOL BEIJINGの理念と名前を受け継ぐ形でスタートした。オープンからの葛藤、そして今の想いについて、メインスタッフである李 鶴群氏、許宸氏、宮﨑洋平氏に話を訊いた。
ライブハウスでもあり、バーでもある。日本のライブハウスだとかなり珍しいスタイル
――まずはそれぞれのポジションを教えてください。
李鶴群(以下、鶴):店長をやっています。スタッフのシフトを組んだり、バンドのブッキングをしたり。手が足りない時はカウンターでお酒を作ったり、ライブの時はセッティングを手伝ったりもしてますね。
宮﨑:SCHOOL TOKYOが今やっているお店のブッキングライブは、中国のバンドが多くて。ほぼ向こうからの留学生とかなんですね。彼(鶴氏)とはブッキングの際、彼らとやりとりをしてもらったり。
許:中国などから来日するアーティストのケアをしていますね。北京と東京を行ったり来たりすることもあります。
宮﨑:SCHOOL TOKYOのルーツになっているのは、18年前に北京でオープンしたSCHOOL BEIJINGというライブハウスで、あちらではかなり知られた存在なんです。そこにゆかりのあるアーティストが来日して、うちでライブをしてくれることも多くて。そういったアーティストたちとのやり取りは、許が窓口になってサポートしてくれています。
――それでは宮﨑さんのポジションとは?
宮﨑:このSCHOOL TOKYOに関わるようになったのは、オープンしてしばらく経ってからです。最初はブッキングを手伝う形で入ったんですが、当時はスタッフが全員中国出身だったこともあり、日本のライブハウスとしての運営の仕方や、現場での進め方を少しずつ取り入れていくことが、自分に与えられた役割でした。正直に言うと、良くも悪くも「ビジネスとしてお客さんに提供できるクオリティ」がまだ整っていない部分が多くて。機材や音響、接客など、まずはそういった環境を整えるところから始めました。それが評価されたのかどうかは分かりませんが、今はSCHOOL TOKYOの日本側の責任者という立場で、運営全体に関わらせてもらっています。
――ありがとうございます。店長の鶴さんからみて、日本のライブハウスシーンはどのように映ってますか?
鶴:私は2010年から日本に住んでいます。それでだいたい10年くらい前から日本のライブハウスでバイトをして。ライブハウスによってカラーがあって、出演するバンドも違っている。それから驚いたのは、音作りのすばらしさでした。中国よりも圧倒的に音がいいんですね。機材や音作りに関しては、今でも勉強しながらやっていますね。

中国のライブハウスシーンを築いた「SCHOOL BEIJING 」という存在
――中国にはライブハウスシーンというのは元々あったんですか?
許:なくはなかったんですが、もっとこう……アンダーグラウンドなカルチャーでした。
鶴:2019年に、日本でいう「イカ天」(1989年~1990年にTBSで放送された深夜番組『平成名物TV』の1コーナー『三宅裕司のいかすバンド天国』のこと。このコーナーから多くのバンドがデビューし、80年代後半のバンドブームをメジャーグラウンドに押し上げた)のような番組が中国で放送されるようになって。そこからバンドをやる人も増えて、中国でもバンドが人気になりましたね。
宮﨑:そもそもSCHOOL TOKYOは、中国・北京のライブハウス「SCHOOL BEIJING」の姉妹店です。“ライブハウス”というものが、中国にまだ存在してなかった頃、“ライブハウス”という文化を根づかせたのが、MAO Live Houseの創設者・千葉和利さんなんですよね。そして、そこで遊んでいたのが、現SCHOOL BEIJINGのオーナーたちであり、それまではライブハウスってものがなくて、飲み屋とかバーで演奏して、それをみてみんなが盛り上がる……みたいな感じだったって聞いてます。
そして実は今のSCHOOL TOKYOの運営には、その千葉さんも深く関わっています。「SCHOOL BEIJING」は中国では名の通ったライブハウスで、そういった空気感や精神を引き継ぎながら、この六本木という街で、また新しいチャレンジをしています。単にライブができる場所というだけじゃなくて、もっと広い意味でカルチャーが交わる場にしていけたらいいなと思っています。
――東京だと、本当に一例になりますが、新宿ロフトだったり、下北沢シェルターだったりと、全国的にも有名なライブハウスが幾つかありますよね。老舗というか……ある意味、ライブハウスシーンのシンボル的なライブハウスっていう意味なんですけど。
宮﨑:バンドマンが憧れるライブハウスっていうことですよね。
――そうです、そうです。そこも含みます。
宮﨑:それが北京では「SCHOOL BEIJING」なんじゃないかな。「SCHOOL BEIJING」は若い子たちの観光地みたいにもなっているらしくて。ドラマのロケ地で使われたり。まぁ……カルチャーの発信地みたいなことにはなってるって聞いてます。
――ブッキングの際のこだわりは?
鶴:正直……今は(スケジュールを)埋めることが最優先で……。知り合いのいろんなバンドにこまめに声をかけているんですけど、なかなか難しいです。
宮﨑:ブッキングにこだわれるほど、流行ってる箱じゃないんで(笑)。正直スケジュールガンガン空いてます(笑)。だからこそ、「こんなイベントやってみたい」「1回だけライブを試してみたい」みたいな人にとっては、めちゃくちゃやりやすい場所かなと。ライブハウスって、どうしても経験者じゃないと出にくいとか、「ちゃんと集客できる人じゃないとダメなんじゃ?」って思われがちなんですけど、うちはそんなことなくて。駆け出しのアマチュアミュージシャンでも、やる気と気持ちがあれば全力で応援したいと思ってます。実際、企画の立て方がわからなくても大丈夫。相談しながら一緒に作っていけばいいし、必要であればチラシのデザインやタイムテーブルの組み方、当日のオペレーションまで、いわゆるマネジメント的な部分も含めてサポートできる体制があります。もちろん「仲間内でゆるくやりたい」とか「カバー曲しかないんだけど…」とかでも全然OK。むしろ、そういう人たちにこそ使ってもらいたい。だから、遠慮なく俺たちを使い倒してほしいですね(笑)。
――鶴さんと李さんに伺います。個人的に呼んでみたいバンドはいるんですか?ジャンルとか、ネームバリューとか、このライブハウスに向いている向いてないとか、全部抜きにして個人的に。
鶴:わぁ、それはいっぱいあります!ジャンルになっちゃうんですけど、ハードコアとかメタル。個人的に大好きなんですよ。普段はそればっかり聴いているくらい。
李:ラッパーですね。ヒップホップが好きなので。特にアンダーグラウンドなディープなヒップホップミュージシャンを呼びたいですね。

音楽で仕事をしたいと思っていた。今それが叶っているから毎日が楽しい
――今、この仕事をしている中で1番嬉しい瞬間を教えてください。
鶴:日本に来てライブハウスで働いていた時に「こういうことをしたいな」「あんなことをしたいな」って思っていたことが、今、体験できていることが幸せ。僕は何度が転職をしてて、音楽以外の仕事もやったりしたんです。だから今、こうやってライブハウスの店長やるなんて想像もできなかった。人との縁って本当に不思議で、運命……とまでは言えないかもしれないけど、したかったことができている、音楽の仕事ができるっていう今の環境にいることに1番幸せを感じます。このライブハウスがオープンした日に、最初のお客さんにドリンクを出した時は、本当に嬉しかったですね。
李:中国から来たバンドがいいライブをした時です。みんないいライブをしてくれるんですけど、ライブ後に話したりすると来て良かったって言ってくれる。
宮﨑:今はまだお店としても発展途中で、ブッキングのスケジュールをどう埋めていくかとか、どうやってより多くの人に知ってもらうかといった課題がたくさんあります。スタッフ同士で日々話し合いながら、少しずつ積み重ねていくしかないかなと。
――ちなみにSCHOOL TOKYOに出演したいと思ったら、やはり問い合わせフォームから音源を送って……?
宮﨑:もちろんです。インスタのDMでもなんでもいい、もう音源なんかなくても大丈夫です(笑)。
――これから積み重ねて作り上げていく、それがSCHOOL TOKYOのコンセプトと言えそうですね。
宮﨑:あとは、中国と日本の間では、すでにたくさんのアーティストが行き来していて、中国のバンドが日本でライブをしたり、日本のバンドが中国で活動する流れは、ある程度できあがってきています。実際にSCHOOL TOKYOに出演してくれたアーティストを、北京やその他の都市でのツアーにアテンドしたこともあります。だからこそ、SCHOOL TOKYOがその中で自然につながる場所になれたらいいなと思っていて。ここでライブをすることが、そのきっかけになったり、次のステップへの後押しになったらうれしいです。中国のアーティストにとっては「いつかSCHOOL TOKYOでやってみたい」と思ってもらえる場所に、日本のアーティストにとっては「ここから先が広がっていく」ような場所になれたらと思っています。
livehouse info
SCHOOL LIVE&BAR TOKYO
- 住所
- 東京都港区六本木5-16-5インペリアル六本木1号館地下1階
- アクセス
- 東京メトロ日比谷線・都営大江戸線 六本木駅 徒歩約4分、東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩約6分
- キャパシティ
- スタンディング250名
- TEL
- 03-5545-5758
- 公式HP
- https://schoolivebar.com/
- ライブ情報
- https://giggs.eggs.mu/livehouse/tokyo/cm98266yv00009gfn4uvwvnp0